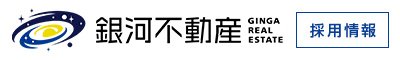相続において「相続人」と「法定相続人」という2つの用語が登場しますが、これらは同じものではありません。相続人は、故人(被相続人)が遺産を受け継ぐ権利を持つ人ですが、法定相続人とは、民法で定められた一定の範囲の相続人を指します。ここでは、相続人と法定相続人の違いをわかりやすく解説し、それぞれの役割や法律上の意義について詳しく見ていきます。
相続人とは?まずは基本を押さえよう
相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産や権利を相続する権利を持つ人のことを指します。遺言がある場合、遺言で指定された人が相続人として財産を受け取ります。一般的に相続人には家族や親族が選ばれますが、遺言書で友人や法人などが指定される場合もあります。
- 遺言による指定が可能:遺言で特定の人を相続人に指定でき、家族以外の人が含まれることもあります。
- 被相続人の意思が反映:被相続人の意思を尊重するため、特定の相続人が財産の一部、または全部を受け継ぐことも可能です。
法定相続人とは?民法で定められた相続の範囲
法定相続人は、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、または遺言が一部しか効力を持たない場合に、法律に基づいて相続権を持つ人を指します。配偶者や子ども、親や兄弟姉妹など、家族や親族が対象であり、法定相続分に従って財産を分配するための基準となります。
- 民法に基づく相続人の範囲:法定相続人は民法で明確に規定されています。
- 相続の優先順位:配偶者は常に相続人となり、子どもや親、兄弟姉妹のうち、どの範囲までが法定相続人となるかは順位が定められています。

相続人と法定相続人の違い
相続人と法定相続人には以下のような違いがあります。
- 選ばれる基準
相続人は被相続人の遺言に基づいて選ばれるのに対し、法定相続人は民法によって範囲が定められています。遺言がない場合には法定相続人が財産を相続することになります。 - 法定相続分の違い
法定相続人には法定相続分が定められており、財産が均等に分配される基準がありますが、相続人の場合は遺言によって自由に配分が決められるため、割合は法定相続分とは異なることがあります。 - 法的な手続きの違い
相続人は遺言に基づいて相続を受けるため、遺言執行者による手続きが必要になる場合が多いです。一方で、法定相続人は民法に基づく法定相続分に沿って自動的に相続が行われるため、遺言がなくても基本的な手続きが進められます。
法定相続人の範囲と優先順位
法定相続人には順位があり、配偶者は常に相続人として優先されますが、その他の法定相続人には以下の順序が定められています。
- 第一順位:子ども
被相続人に子どもがいる場合、配偶者と子どもが法定相続人となり、配偶者が半分、子どもが残りを等分します。 - 第二順位:直系尊属(親など)
子どもがいない場合、親が法定相続人となり、配偶者と親で財産を分けます。 - 第三順位:兄弟姉妹
子どもや親がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となり、配偶者と分け合います。
法定相続人の「法定相続分」とは?
法定相続分とは、法律で定められた相続人ごとの相続割合のことです。たとえば、配偶者と子どもが法定相続人の場合、配偶者は1/2、子どもは残りの1/2を等分して相続します。法定相続分に従って財産を公平に分配することで、相続トラブルを未然に防ぐ効果もあります。

不動産相続時に必要!相続登記とは?
不動産を相続した場合、所有権を正式に相続人に移す「相続登記」が必要です。この手続きをしないと、不動産が未登記のままになり、売却や権利の行使が難しくなるため、手続きの流れや注意点を知っておきましょう。
相続登記の流れ
- 必要書類を準備する
戸籍謄本や被相続人の住民票除票、遺産分割協議書(協議が行われた場合)などを準備します。 - 登記申請書を作成
法務局で申請するための「登記申請書」を作成します。法務局のウェブサイトでも雛形が提供されています。 - 法務局へ申請
登記申請書と必要書類を法務局に提出します。法務局に直接持ち込むか郵送でも提出可能です。 - 登記完了証の受領
手続きが完了すると「登記完了証」が交付され、所有権が正式に移転されます。

相続登記の注意点
- 期限はないが早めの手続きを
相続登記には法的な期限はありませんが、放置すると権利関係が複雑化し、他の相続人や第三者とのトラブルの原因になります。 - 遺産分割協議の重要性
複数の相続人がいる場合、事前に「遺産分割協議」を行い、誰が不動産を相続するかを決めておくことが必要です。 - 持ち分の共有問題
登記を複数人の共有名義で行うと、後の売却や分割が複雑になり、トラブルの原因となります。 - 相続人の所在不明
相続人が多い場合、一部の相続人の連絡先が不明だったり、海外在住の場合、協議が困難になります。 - 費用が発生する
相続登記には登録免許税などの費用がかかります。税額は不動産の固定資産税評価額の0.4%で計算されるため、事前に確認しておきましょう。
相続登記しないリスクとは?
- 売却や融資ができない
登記がされていないと、不動産の売却や担保設定ができず、資金調達や処分が困難になります。 - 所有権が不明確になる
登記をせずに放置すると、相続人が亡くなり、新たな相続人が増え、所有権が複雑化して相続が難しくなります。

まとめ:相続人と法定相続人を正しく理解し、円満な相続を実現しよう
相続人と法定相続人は似た言葉ですが、法律上で異なる役割を果たします。相続人は遺言によって指定された相続者であり、被相続人の意思を反映するものです。一方、法定相続人は、民法に基づいて相続の範囲や割合が決まっています。円満な相続を実現するためには、相続人と法定相続人の違いを正しく理解し、それぞれの権利や義務を尊重することが大切です。
また、不動産を相続した時の相続登記については、不動産の所有権を正式に移転する重要な手続きです。事前に流れや必要書類、注意点を把握しておき、遅れなく登記を済ませることが、トラブルのないスムーズな相続につながります。