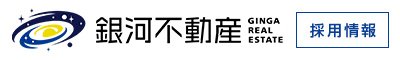親が亡くなり、遺言書を発見した際には、いくつかの手順と法的考慮が必要です。親族間のトラブルを避けるためにも、遺言の内容をしっかりと理解し、正確な手続きを行うことが大切です。ここでは、遺言書の効力や、相続における遺留分について解説します。
遺言書を発見したらどうしたらいい?
親が亡くなった後、遺言書が見つかることは珍しくありません。しかし、遺言書の内容をただ受け入れる前に、いくつかの確認が必要です。遺言書には以下の種類があり、手続きが異なります。
- 公正証書遺言:公証人によって作成された遺言書で、家庭裁判所での検認は不要です。
- 自筆証書遺言:本人が自筆で書いた遺言書で、家庭裁判所での検認が必要です。
- 秘密証書遺言:内容が秘密にされ、家庭裁判所の検認が必要な遺言です。
遺言書を発見した場合、遺言の種類に応じて、家庭裁判所で「検認手続き」を行う必要があるかどうかを確認しましょう。

検認手続きとは?
検認手続きは、遺言書の偽造や改ざんを防ぐための確認作業です。家庭裁判所で検認を行うことで、遺言書が正式なものとして取り扱われるようになります。検認手続きは遺言書の有効性を判断する手続きではなく、遺言書の存在や内容を確認するためのものです。
たとえば、自筆証書遺言の場合、親が亡くなった後に遺族が発見しても、そのまま効力を発揮するわけではありません。まず家庭裁判所で検認を行い、その後に相続手続きを進める流れとなります。
遺言の効力を争う場合
遺言書が見つかっても、その内容に疑問や不満がある場合、遺言の効力を争うことも可能です。遺言の効力を争うためには、以下の要件を確認しましょう。
意思能力の欠如:遺言が作成された時点で、被相続人(故人)が意思能力を欠いていた場合も、無効を主張できる場合があります。
遺言の方式違反:遺言書が法律で定められた方式を満たしていない場合、その効力が無効になる可能性があります。
偽造・改ざん:遺言書が偽造されている場合や、第三者によって改ざんされた場合、家庭裁判所でその証拠を提示することで、無効の判断を求めることが可能です。

遺留分とは?
相続において、被相続人が遺言で全財産を特定の相続人に渡すと指定していたとしても、他の法定相続人には「遺留分」と呼ばれる最低限の相続権が保障されています。遺留分は、特に親族間の公平な相続を守るために法律で定められた割合であり、特定の相続人が法定相続分を大きく下回ることを防ぐためのものです。
遺留分侵害額請求の手続き
遺言によって遺留分が侵害されている場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことで、自分の遺留分を取り戻すことができます。これは、遺留分に相当する金額を特定の相続人から金銭で請求するための手続きです。
遺留分侵害額請求の流れ
- 通知:遺留分が侵害されているとわかったら、相手方(主に遺言によって多く相続を受けた相続人)に対して、遺留分侵害額請求の意思を示します。
- 交渉:多くの場合、遺留分侵害額をめぐって相続人同士での交渉が行われます。ここでの話し合いが難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。
- 調停や訴訟:交渉が成立しない場合、家庭裁判所に調停や訴訟を起こして遺留分侵害額の確定を求めます。
遺留分侵害額請求の期限
遺留分侵害額請求には期限があり、遺留分が侵害されていると知った日から1年以内、または相続開始(被相続人の死亡)から10年以内に請求しなければなりません。この期限を過ぎると遺留分侵害額請求の権利は失効します。
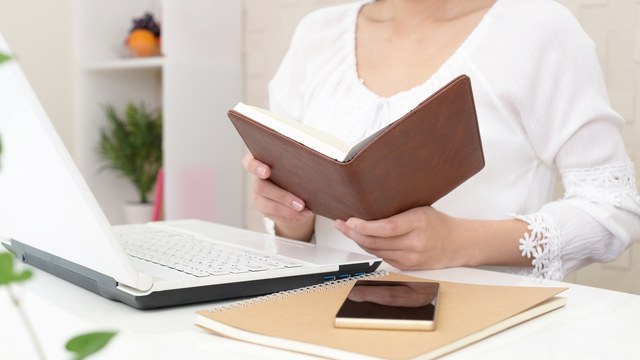
遺留分が侵害されるケース
たとえば、以下のようなケースを考えましょう。
- 家族構成:母、長男、長女
- 遺言の内容:「すべての財産を長男に相続させる」
- 財産:現金1,000万円
この場合、長男がすべての財産を相続することになりますが、長女には遺留分の権利が認められます。
子のみの相続になるため、遺留分は2人で2分の1(500万円)。兄妹2人ですので、一人当たり250万円となります。
長女は250万円の遺留分が保障されていることになります。長女は遺留分侵害額請求を行うことで、長男から250万円を請求できる権利が発生します。
公正証書遺言と遺留分
公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、その法的効力は非常に強固です。そのため、公正証書遺言の内容を無効とするのは難しいとされています。しかし、遺留分を主張することは可能であるため、たとえ公正証書遺言が存在しても、遺留分侵害額請求によって自分の権利を守ることができます。

まとめ
親が遺言書を残していた場合、次の手続きを行うことで、相続手続きを円滑に進めることができます。
- 遺言書の確認:遺言書の種類(公正証書、自筆証書、秘密証書)を確認します。
- 検認手続き:家庭裁判所で検認が必要な場合、速やかに手続きを行います。
- 遺留分侵害額請求:遺留分が侵害されている場合、相続人は遺留分侵害額請求を行うことで、自分の遺留分を確保します。
- 専門家への相談:遺言や遺留分で争いが生じた場合、弁護士や司法書士に相談することで、適切な対応を図ることができます。
親が遺言書を残していた場合、内容の確認とともに「遺留分」や「検認手続き」を進めることが大切です。遺言書の種類に応じた手続きを行い、法定相続分が保証されているかを確認しましょう。遺留分が侵害されている場合は、「遺留分侵害額請求」によって自身の相続権を確保する方法もあります。家族間のトラブルを避け、公平な相続のためにも専門家の支援を受けて冷静に対応しましょう。